MAGAZINEあそびのもり
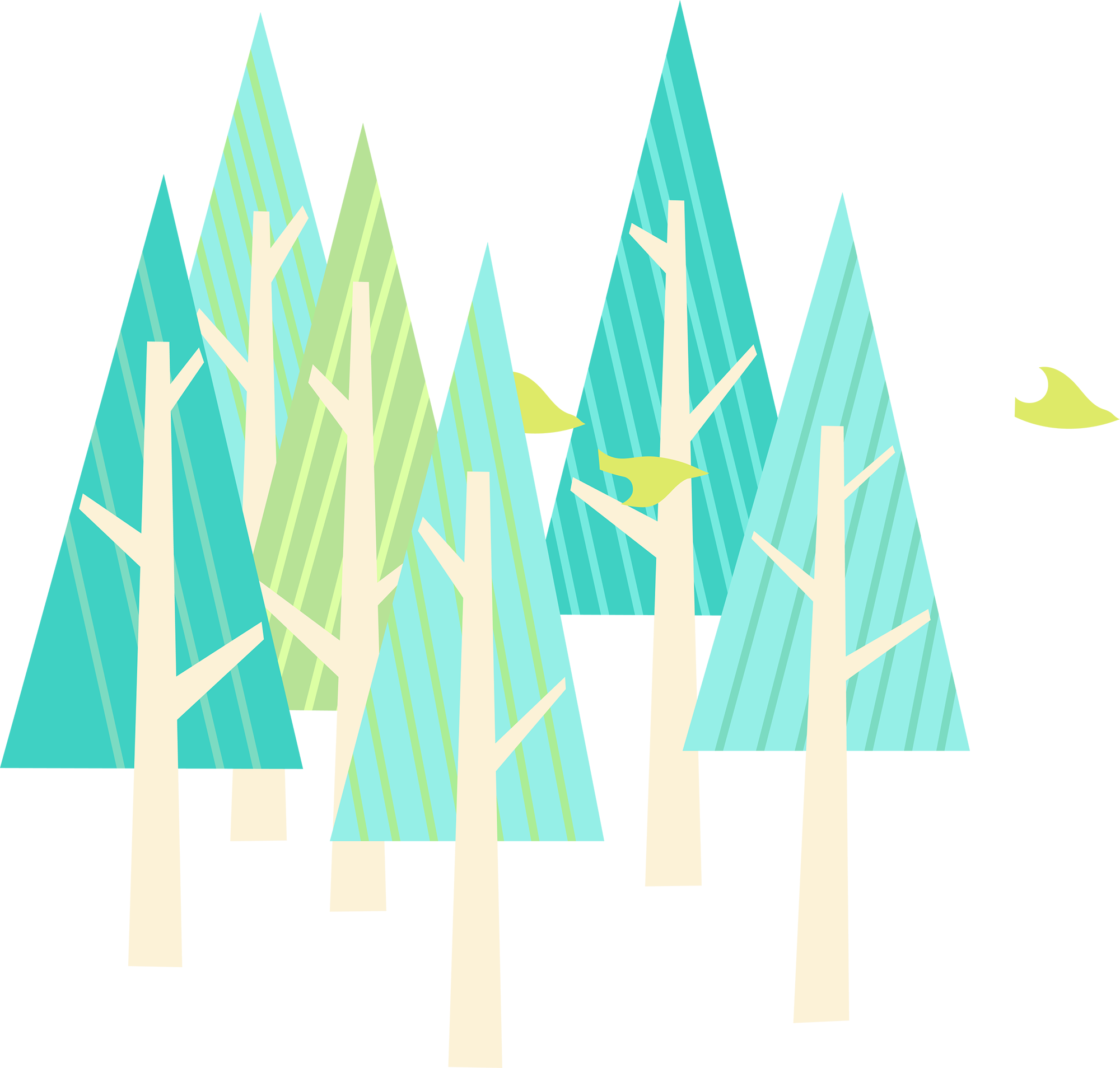

子ども達はなぜ砂場に
夢中になるのか
#子育て#あそび

時間を忘れて何かに夢中になること。
小さな子ども達の成長にとって、それはとても大切な時間です。
私たちボーネルンドは、あそびを通じて子どもたちに「好き」や「夢中」を見つけてほしいという思いで、あそび道具やあそび場をお届けしてきました。
この特集では、そもそも「夢中になること」がなぜ私たちにとって大切なのかを、有識者の皆さんにお話を伺いながら考えていきます。
今回は、砂場研究で知られる笠間浩幸先生に、子ども達がなぜ砂遊びに夢中になるのか、その理由についてお話を伺いました。
お話を
聞いた方
笠間浩幸先生
同志社女子大学現代社会学部現代こども学科特任教授。幼児教育学で教鞭をとるかたわら、「砂場と子ども」について30年以上にわたって研究。近年は大人が砂遊びを楽しみ、その魅力や意義を知るためのワークショップ「プレイフル・サンドアート」も主宰。著書に『<砂場>と子ども』『保育者論』『砂砂砂』など。
子どもはなぜ砂場に夢中になるのか
砂場研究の第一人者として知られている笠間浩幸先生。研究を始めたきっかけは、ご自身のお子さんが砂場で砂遊びに没頭する姿を目のあたりにしたことでした。
当時3歳だった娘が砂場で1時間近く、真剣に遊び続けていることに心から驚きました。砂場研究を始めたのは、そのときに感じた2つの大きな疑問を解き明かすためです。
1つめの疑問は、砂遊びのいったい何がそんなに3歳の子どもを夢中にさせるのかということ。
2つめは、単に砂が集まっているだけの場所が、どうして子どものための遊具として普及しているのか、そもそも誰がどのような意図で作ったんだろうという疑問です。
2つめの疑問については、さまざまな文献にあたって砂場の歴史を探ることから始めました。その中でデンマーク人が1909年に書いた砂場の本に出合います。ドイツやアメリカの、当時の古い砂場の写真をたくさん残してくれていました。あんな貴重なものを100年前に残してくれた人がいて、100年後の私がそれを読ませてもらえていることに今でも感動していますし、自分の課題は、この砂場をこれから100年後の子ども達に残すことだと思っています
30年にわたる研究の結果、砂場には200年近い歴史があることが明らかに。砂場の歴史の全容も、ほぼ解明できたと笠間先生は感じているそうです。
1つ目の疑問である「なぜ子どもは砂遊びに夢中になるのか」についても、保育園での定点観測などを通じて、子ども達の成長につれて砂遊びがどのように変化していくのかを、長年にわたり分析し研究してきました。
砂遊びは子ども達の発達段階に応じて進化していくあそびであり、その中で子どもが自分の力を最大限に引き出されていることがわかりました。また、そうした発達的視点だけでなく、砂遊びには自分を受け入れてもらっている心地良さや、感覚への刺激、トライ&リトライを繰り返しやすいといった魅力があることもわかってきました
“フロー体験”理論との出会い
それらの魅力が、どうして子どもの夢中につながるのでしょう。ある理論に触れたことで、そこに新たな気づきがあったと笠間先生は続けます。
心理学者のミハイ・チクセントミハイによる「フロー体験」(※)の理論です。「夢中になる」って、すごく抽象的ですよね。主観的であり感覚的でもあります。一人ひとりの感性によって違う領域で、科学的な解明は無理なのではないかと私は思っていました。それがこのチクセントミハイによって、ここまで研究されていたことにとても驚きました。机上の議論ではなく、何千人ものデータを実際に集めて分析している。この理論に出会うことで、「子どもがなぜこんなに砂場に夢中になるのか」という30年来の疑問が解けたように感じています
- フロー体験:心理学者ミハイ・チクセントミハイが提唱した理論で、ある活動に深く没頭し、時間を忘れるような状態を指す。この理論は幸福学の観点からも重要視されており、幸福な人生を送るための要素として注目されている。
砂場遊びがもたらすフロー体験
フロー体験を構成する要素はいくつかありますが、特に以下の4つが重要とされています。
- 適切な難易度:自分の能力に対して適度に難しく挑戦の余地がある
- 自己制御感:自分で決めて行動できる
- 素早いフィードバック:結果がすぐに見える
- 集中できる環境:没頭しやすい空間
笠間先生は、このどれもが砂遊びに含まれていると考えています。
発達的視点でいうと、まず乳児期にはカップに砂を出し入れするなど、道具が主役のあそびが始まります。私はこれを「砂で遊ばない砂遊び」と呼んでいます。そして1歳台後半からは砂そのものに興味が出始めます。2歳を超えて手指を上手に動かせるようになると、道具や砂の扱いもうまくなり、水を使うことを覚えます。水と圧をかけることで砂が固まることを知り、型抜きや泥団子づくり、砂山づくりなどが始まります。3歳ともなると、砂を別のものに見立てたごっこ遊びに発展。プリンやケーキに見立てて、甘いよ!おいしいよ!と友達や大人とのコミュニケーションが始まります。
このように、砂遊びには挑戦の段階が非常にたくさんあります。0歳児から年中年長、小学校から大学生、さらには大人の領域まで、どんなレベルでもそれなりに遊べて、挑戦もできる。だから子どもは絶えず自分の能力を確認できるし、もうちょっとやってみようという挑戦もできるのです。
砂場に入った子どもは、穴を掘ったり砂山や泥団子を作ったり、自分のやりたいことに向かって一心に遊び始めます。自分が決定者であり、自分の興味関心にまっすぐ一直線に進んでいく。砂は柔らかく自在に形を変えて、子どもの力をそのまま受け止めてくれますから、自分で自分の意欲に従って遊べるのです
たしかに、砂場はフロー体験の要素を自然と満たしているようです。
加えて、感覚的で直接的な刺激にあふれていることも砂場のポイントです。サラサラだったりぐちゅぐちゅだったりといった触り心地、水をかけると色が変わったり、高さを出すことで光と影を見つけたり、山が一瞬でつぶれてなくなったりするのはとても興味深い視覚刺激となります。そしてバケツに入れて振ったときのシャキシャキという音。砂場は感覚を直接刺激してくれるのです
感覚を刺激する砂場は子ども達の心を深く捉え、没頭に導きます。砂場で夢中になっているとき、子ども達はまさにフロー状態にあるのではないか。笠間先生はそう考えています。
砂場で子どもが夢中になるために親ができること
ここまでの記事を読んで、いますぐにでも砂場にお子さんを連れていきたくなった親御さんも少なくないでしょう。一方で「うちの子は砂遊びにあまり興味を示さない」いう場合もあるかもしれません。
砂を嫌がるお子さんは多いですよ。砂の感触は刺激も強いですから、ある意味当たり前のことです。それを無理やり遊ばせようとするのではなく、あえてお子さんを無視してでも、まず親御さん自身が砂遊びを楽しんでみてください。道具や水を使っているうちに、気づけば大人の方が砂遊びに没頭しているかもしれません。そんな親御さんの姿を見ると、子どもも興味をもって自分から砂に手を出すようになります
そうして子どもがやっと砂を触ってくれたら、つい「トンネル掘ろう」「階段を作ろう」と誘ってしまいそうだが、それはいったん、ぐっと我慢。まずは、子どもがどんなことに興味を持ったのかを、しっかり見守ることが大切です。
子どもは、自分で見つけたものに夢中になります。親が熱心に何かを作っているのを見た子どもが、もし「やってみたい」と言ってきたら、そのときに一緒に楽しめばいい。親はちょっとだけ先回りして、子どもが挑戦のできる環境を作り、あとは反応を横目で見守っているのがよいと思います
幸せな体験、そして幸せな人生とは
砂場で夢中になっているとき、子どもはフロー状態にあるようです。幸福学において、フロー状態を体験することは幸せな人生を送るための大切な要素のひとつとされています。それはいったい、どんな幸せなのでしょう。
自分自身で自由に楽しさを見つけて、自分の思いで挑戦ができる。そしてできた!と自分を認められる。それを続けていけることこそが、幸せな人生なのではないでしょうか。幸せへの第一歩は、絶対に自分の中にある。自分自身に手応えを感じられる、自己の行為そのものの中に楽しさを見いだせる。その手応えや楽しさは内的報酬として自分へのご褒美となり、それが次の学びへの意欲となるのだと思います。
学び続けられるということは、成長し続けている自分を感じ取れるということ。これは何歳になっても楽しいことですよね。そういった経験を子ども時代にたくさんしておくことは、非常に大切なのではないかと思いますね。
大人向けの講演会であそびとは何か、というテーマでお話するとき、参加者の皆さんに子ども時代のあそびを思い出してもらうことがあるのですが、皆さん必ず、とてもにこやかな表情になります。つまらなそうな雰囲気になんて絶対になりません。これはもう、皆さんが子ども時代のあそびに幸福を感じているのだとしか思えないわけです。大人になって年を取ってからも、子どもの頃のあそびを思い出すとみんなニコニコ笑顔になる。これこそ幸福のそのものじゃないかと思います
子ども達が夢中になれる経験をたくさん積み、成長する過程で自信や達成感を育んでいく。それはきっと、未来の幸せな人生につながる大切な基盤に。砂場で砂遊びに没頭するような、親子で一緒に夢中になれるかけがえのない時間を、子どもと育んでいきたいですね。


